イヌやヘビがもつ異次元の嗅覚能にフェルミ推定でせまる
世界を把握するための3大五感を比較
視覚という感覚器は「光」、聴覚は「音(空気の振動)」がもたらす物理的情報に「意味」をあたえる。そして嗅覚は、「空気中の分子の濃度」に意味をあたえることになる。どうしてもわたしたち人間は、視覚>聴覚>嗅覚という順番で、より精密な世界の情報をおしえてくれると思いがちだが、実際には、これらの感覚には一長一短がある。
たとえば視覚の最大の欠点といえば、夜に機能しなくなるという点だ。人間のように電気を発明して、暗闇を照らすほどのエネルギーをあやつれるようにならないかぎり暗闇で役にたたない。深海生物やホタルなど一部の昆虫には蛍光能力があるいきものもいるが、暗闇を照らして見えるようにするためにこの能力をつかっているいきものはいない。かれらは、天敵への威嚇や求愛のため、つまり相手に自分を見せるために光を使っていて、自分が見るためではない。闇を照らすための発光には莫大なエネルギーがいるため、進化のパワーをもってしても難しいらしい。
聴覚について考えよう。聴覚の利点といえば、空気の振動をひきおこすものならなんでも、遠く離れていても感知することができる点にある。物陰にかくれた天敵が枯れ葉をふんだ音を即座にききとったり、数十キロはなれた川がどっちの方角にあるかつきとめることができるものもいる。物理的に見えないはずのものでも、聴くことはできるというわけだ。
しかし、聴覚の大きな欠点といえば、空気を振動させる類のものしか認知の対象とならないことだ。視覚や嗅覚と比べると、この点が決定的に違う。コウモリやアナツバメのエコロケーションだけは例外で、前述のような、自らが光を発して足元を照らすのに相当することを、音波をつかってやっている。光と違ってそれが可能になるのは、音波の場合、生成することが比較的かんたんだからだ。でかい声で叫べばいい。これによって、かれらはおそらく驚くほど正確な立体空間認識能をもっているだろう。とはいえ、エコロケーションをもってしても、目の前に熟した果物があるかどうかは聴覚だけではわからないだろう。
嗅覚は、これらの五感とくらべると、つかみどころがなく、とてもあいまいなことしか知ることができないように思える。目の前の人が笑っているかどうかということでさえ、嗅覚からはなんの情報もえられないのだ。
とはいえ、わたしたち哺乳類は(特に鳥類と比べて)嗅覚を特に発達させてきた動物である。恐竜の時代に、夜行性戦略をとることで恐竜との直接対決を避け、繁栄してきたという背景があるため、視覚にたよることがあまりできなかったのだ。実際に、ほとんどの哺乳類では嗅球という嗅覚情報を処理する脳の一部は、嗅覚受容体と直接つながっており、五感のなかで特別扱いとなっている*1。ところが進化の過程で、霊長類はとりわけ、嗅覚の精度を落とし、視覚を強化することになった。だから、今のわたしたちは嗅覚という感覚をあまり重視しないのかもしれない。
イヌやヘビがもつ嗅覚の謎
警察犬は、数キロにも渡って、においを手がかりに足跡を正確にたどり、ターゲットを見つけ出してしまう。
ヘビはにおいを味わうように、舌をシュルッと出して、空気中の化学物質を味見する。それによって獲物の居場所をつきとめ、追跡し、どちらの方角に逃げていったかもわかるらしい。ヘビに見つかって一度は逃げきってネズミやウサギも、そのにおいを辿られて結局巣穴を特定されてしまうことがある。
嗅覚を比較的退化させてきたヒトから見ると、これらの動物の嗅覚には驚きだ。小さいころから不思議に思ってたが、どうしてこんなことが可能なのだろう。歩いただけ、存在しているだけのターゲットを追跡できるのはなぜなのだろうと。
この疑問を解決してくれたのには、2つの視点がある。感覚器の潜在的パワーと、フェルミ推定だ。
感覚器の潜在能力
「ゾンビでわかる神経科学」で知ったのだが、人間の五感はわれわれが思っているよりずっとすごい分解能をもっているらしい。なんと人間の視覚は、数個の光子を識別可能だという*2!聴覚の感度にも驚くべきものがある。わたしたちが、右から聞こえた音と左の音の方角がわかるのは、時速1200kmという音速でかけぬける波が、0.0何秒というタッチの差で鼓膜を揺らすタイミングのずれを認識できているということだ。
進化がつくりだす生物機械はこの世に存在する手がかりはなんでも、識別できるようになるのかもしれない。それが生存競争において有利であるかぎり。
だが、感覚器におそるべき潜在能力があることはわかっても、もう一つの疑問がのこる。そもそも、においの元となる手がかりがなくては、足跡を追跡することなどできないはずだからだ。ということで次は、わたしたちが存在するだけでこの世界にどれだけの爪痕を残しているのか、ということをフェルミ推定で考えよう。
フェルミ推定
ローマ帝国の指導者ユリウス・カエサルは、「ブルータス、おまえもか」の一幕としても知られているように、暗殺されてしまうわけだが、そのカエサルの最期の一息に含まれた分子を、今このブログを読んでいる間に、わたしたちが吸っている確率は何%だろうか?
なにやら興味をひくへんてこな設定のクイズだが、この模範解答は驚きとしかいいようがない。こたえは、ほぼ100%だ*3!!
どうしてこんなことがわかるかといえば、人が一度の呼吸で吸って吐く息の体積をわりだし、地球の大気中の粒子数を概算し、密度を計算し。。。ということをやると、厳密な値はわからなくとも、そのスケールを推定できるということだ。これがフェルミ推定のすごさだと言える。
Further physics - The last breath of Caesar
このスケールがわかれば、嗅覚の限界についても推定することがだろう。「今朝マクドナルドを食べた男性が30分前にこの通りを通った」といったことがわかるようになるかもしれないし、イヌはすでにそういうことを思っているかもしれない。
個人的にとても興味をひいたのはちょっとまえNHKで放送していた「スニッファー 嗅覚捜査官 | NHK 土曜ドラマ」というドラマだ。異常に嗅覚の鋭い人間(阿部寛)がにおいを手がかりに凶悪事件を次々と解決するという話なのだが、わたしには、これがかなり未来予言的なSFに見えた。
嗅覚にあって、視覚と聴覚にはない、大きな特徴の一つは、減衰時間の長さだ。光や音といった波は時間とともに急激に減衰し、もはやなんの手がかりも残さなくなってしまう。犯人がここにいた、という情報が残像や残響でのこるということはないが、においであれば、それがある。

Caesar's Last Breath: Decoding the Secrets of the Air Around Us
- 作者: Sam Kean
- 出版社/メーカー: Little, Brown and Company
- 発売日: 2017/07/18
- メディア: ハードカバー
- この商品を含むブログを見る

- 作者: ティモシー・ヴァースタイネン,ブラッドリー・ヴォイテック,Kousuke Shimizu,鬼澤忍
- 出版社/メーカー: 太田出版
- 発売日: 2016/07/20
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
狂犬病がもたらした知見、強固な記憶はいかに作られるか
狂犬病は、もっとも致死率の高い病気としてギネスに登録されている。発症後に助かった記録は歴史上数えるほどしかないというおそろしい病気だが、罹患後の典型的な症状として興味深いものがある。「水」や「風」などのなんということもない刺激をおそれるようになるのだという。かとおもえば、凶暴化して、かみつくようになったりと、狂ってしまったかのような印象を与える。
実際に狂犬病ウイルスは脳を蝕む。このときの脳の炎症が「情動(原始的な感情)」に損傷をあたえているのではないか、と考えた学者がいた。意味もないことに怒り、意味もないことに恐怖をかんじるというのは情動に異常があると言えそうな状況だ。
アメリカの神経科学者ジェームズ・パペッツは、狂犬病にかかった人の脳を詳しく調べ、それらが、視床、帯状回、海馬などにダメージを与えていることをつきとめた。そしてこの一連の脳作用が情動をうみだすエンジンとなっているのではないかと仮説をたてた。のちにここに扁桃体が加えられるなど改善され、大脳辺縁系と名付けられる。
そしてこの回路は、情動に関係するだけでなく、のちにエピソード記憶の形成にも大きな役割を果たしていることがわかってきた。情動と記憶は、脳の構造によってきってもきりはなせない関係にある。PTSD、トラウマなどがそうであるように、つよい情動に起因して、鮮烈な記憶が残るという仕組みがおそらくここにある。

- 作者: ティモシー・ヴァースタイネン,ブラッドリー・ヴォイテック,Kousuke Shimizu,鬼澤忍
- 出版社/メーカー: 太田出版
- 発売日: 2016/07/20
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
ここで、「カラスの科学」で紹介されていた興味深い例を紹介したい。
ノーベル賞受賞者で、動物愛護の巨匠としても知られる動物行動学者のコンラート・ローレンツには、めんどうを見ていたとあるカラスがいた。このカラスは長いこと行方不明になったのちローレンツのもとに戻ってきて、彼に向かってドイツ語でこうしゃべったという。
「すっげえ罠でやつをつかまえてやった!」
カラスが人間の言葉をしゃべるのか、ということに疑問をもった人は、「カラスの科学」でも、その他多くの本でも事例が紹介されているので、確認してみてほしい。もしかしたらYouTubeにもカラスがしゃべる動画があるかもしれない。オウム、インコ、キュウカンチョウをイメージすれば、驚くことではないか。
しかし私が驚いたのは、このカラスは行方不明のあいだおそらく人間につかまっていたという点にある。だとすると、このカラスは驚くほど文脈をとらえた発言をしている!まるで自虐ネタか、ブラックジョークのようにもきこえてくる。カラスが人間の言葉をまねできるのはわかるとしても、言葉の意味を理解しているとしたら大変なことだ!
よくよく読んでいくと、このカラスは自分をつかまえた人間が、そのときしゃべっていた内容をまねしているのだということがわかった。カラスは人間につかまるという、恐ろしい体験の下で、人間が発したなにげない言葉を一瞬で、実に正確に、そして鮮明に記憶したということだ。
鳥類と哺乳類は生命の進化樹にあてはめるとかなり遠い距離にあり、脳の構造は互いに異なる部分も多いものの、情動と記憶が密接にかかわるということは共通しているようだ。脊椎動物になってからすでに手にした性質なのかもしれないし、もしかすると、収斂進化しているという可能性もあるかもしれない。恐怖などの情動をつくりだすこと、そしてそれを状況記憶とむすびつけることが、生存競争下で非常に重要だったのだろう。
わたしはといえば、特定の音楽をきいたり、においをかいだりすると、過去その刺激にあったときの記憶がばっとよみがえることがある。たいていそのような記憶は、すごく嫌な時期だったり、不安をかかえていたり、悲しい時期だったことが多い。
ある人が亡くなる直前、よくお見舞いにかよっていた道中でよく聴いていた曲は、明るく愉快な曲にもかかわらず、いまだにその曲を聴くと泣いてしまうことがある。
ネアンデルタール人はしゃべらなかった。そんなことありえる?
「ネアンデルタール人 言葉」などでググるとわかるが、ネアンデルタール人はしゃべらなかったと思っている人がわりと多い。だが、そんなことありえるだろうか?
...厳密にはありえる。ネアンデルタール人は言葉を話さなかったという可能性もゼロではない。でも、ゼロではないからといって、どうして彼らがしゃべらなかったという可能性をことさらに強調するのだろうか?
...その意図もわかる。わかりやすいストーリーを作りたいのだ。ホモ・ネアンデルターレンシスには言葉がなく、ホモ・サピエンス*1には言葉があった。その差が競争を有利にし、ホモ・ネアンデルターレンシスは絶滅し、ホモ・サピエンスは生き残ったと。
だから、こういった主張をするのは、言語の起源を研究をしていたり、言語を軸にホモ・サピエンスのアイデンティティを定義しようとする人たちに多いだろう。
だが、わたしから見ると、この類の推論はきれいなストーリーを作りたいあまり、的をえていないように思える。なぜそう思うか、それは、人類とネアンデルタール人の石器の変遷を見ればわかる。
ネアンデルタール人とホモ・サピエンスの石器の変遷
人類の石器時代は、おおまかにいって、
に分けられ、さらに旧石器時代は、
に分けられる。このトピックにとって非常に重要な時代は、中期旧石器時代および後期旧石器時代だ。
ネアンデルタール人が地球上に現れたのは約40万年前、ほろびてしまったのは約3万年前だ。大半は中期旧石器時代に該当し、後期旧石器時代にさしかかっている。この時期、ネアンデルタール人や同時代のわれわれの祖先が使っていた石器は、荒々しいハンドアックス、そして道具としては一段階進歩を遂げた剥片石器というものだ。
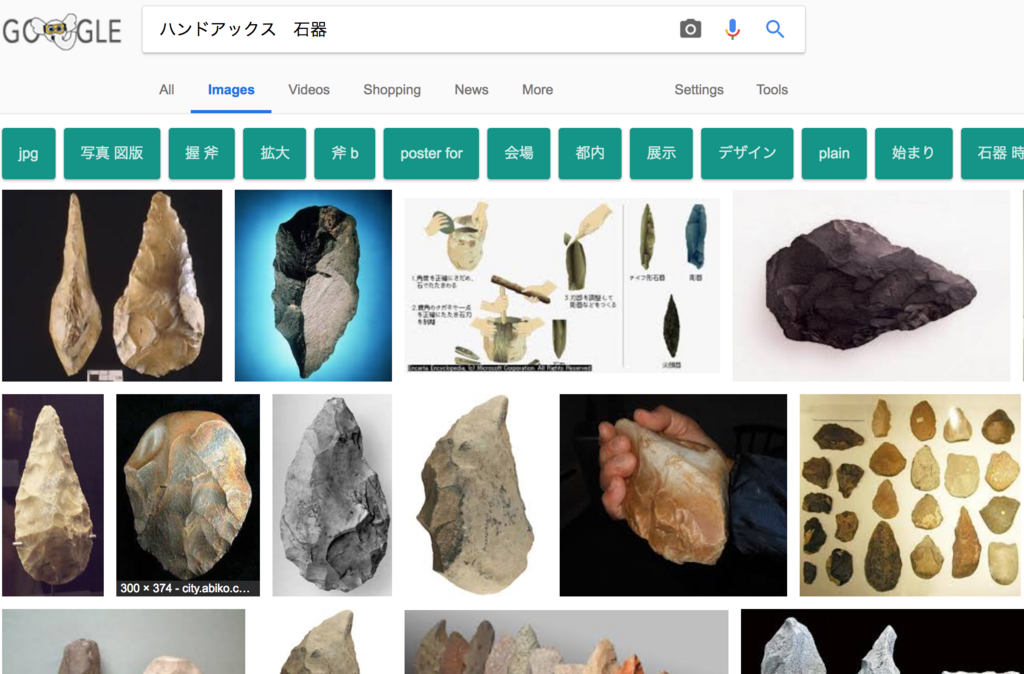

これらの石器におもしろさを見出せる人は学者以外にはすくないと思うが、もっとも重要なこととして、数十万年という長い同時代をともにしたネアンデルタール人とホモ・サピエンスは、その大半を両者とも多様性にとぼしい文化を営んですごしていたのだ。これは遺跡の記録からあきらかなことなのだ。約4.5万年前(後期旧石器時代にさしかかる時期)より以前の遺跡には、剥片石器よりも洗練された石器は出土しない!!つまり、その時代にいたのが誰だろうが、ホモ・サピエンスも、ネアンデルタール人も、デニソワ人も、ホモ・エレクトスも、はたまたチンパンジーも、4.5万年前以前は、誰もが原始的な技術力しかもちあわせていなかった。
ところが、約4.5万年前あたりから、ホモ・サピエンスが所有する石器だけが急激に洗練され始める。ちょうど以下のような具合に。多様な石器が次々とあらわれ、用途が専門家されていくことがわかる。
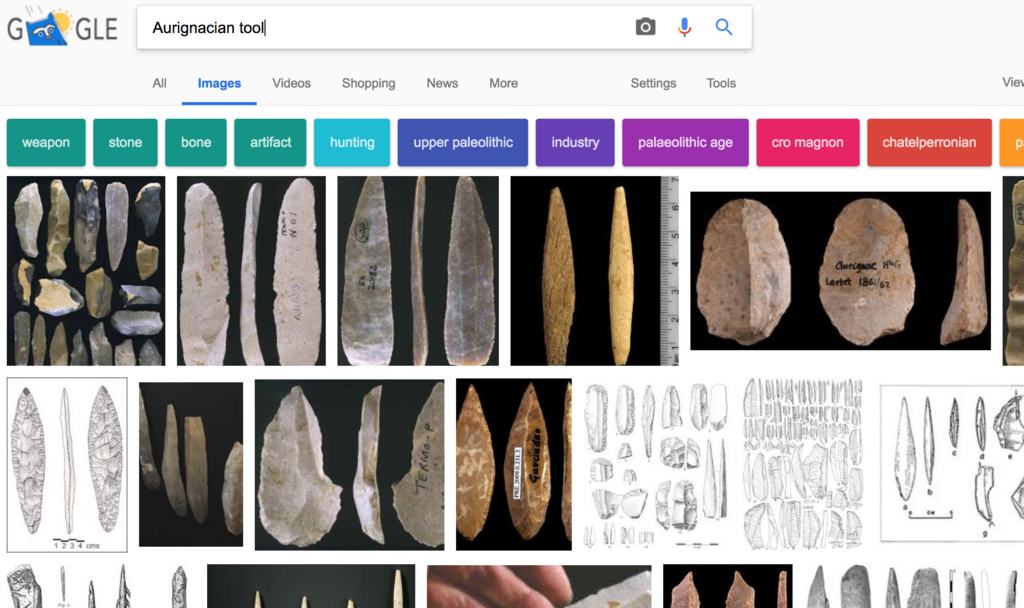
時系列でまとめる
さて、今私たちが手にしている情報を時系列にまとめよう。

ホモ・サピエンスがその祖先であるホモ・エレクトスから進化したのは約20万年前といわれている。解剖学的に現在の人類とかわらない存在は、登場以来少なくとも15万年ほど、原始的な石器をつくり続けた。これが示唆していることは、いささか衝撃的ですらある。わたしたちは、今手持ちの継承文化をすべて失うと、どんなにがんばっても原始的な石器しか作れようにならず、しかもそれが10万年以上も続く可能性が高いわけだ。
数十万年という気が遠くなるほど長い間、さしてかわりばえのしない石器を作り続けてきたという事実は、コミュニケーションの質を推測する上でおそらくもっとも重要な手がかりだ。少しでもこの二大人類に言葉の質の違いがあったとするなら、彼らがつくる石器にもその違いが反映されていないとおかしい。それが数十万年に渡って見られないということは、同じレベルの言語能力だったと考えるしかない。少なくともそれがわれわれの生活をかえたり、生存確率をかえるような、意味のある差でないことはあきらかである。
こう考えると、ネアンデルタール人がわれわれよりも”あきらかに”劣っていたと考えることは、相応の根拠がない限り、無理矢理感が強いことがわかってもらえると思う。
約4.5万年前なにがおこったのか
しかしそれと同時に、こうして時系列で見ると、約4.5万年前、なにやらただごとでないことがわれわれの身におこったこともあきらかだ。このときわたしたちは急に思いついたかのように、アフリカをとびだし、次々と大陸に進出し、海を渡り、洗練された石器をつくり、犬を飼いならし、洗練された武器をつくり、芸術作品を数多く作り始める。今の私たちからみても文明とよべるものが、ついに動き出す。そして、これと時を同じくしてネアンデルタール人が絶滅するのだ。
このとき一体なにがおこったのか?
わたしはそのこたえが知りたくてしようがない。その真相は残念ながら謎のままだが、問題解決能力の飛躍的な向上、文化伝統の飛躍的な蓄積がおこっていることを考えると、以下のようなことのいずれか、またはいくつかがおこっているのではないかと推測できる。
- 人口増加
- 長寿命化
- 手先の器用さの進化
- 言葉の進化
前述のように、脳容量などといった大きな違いは約20万年前から現在に渡って、生まれていない。(むしろ脳容量は現代までの間小さくなっている)この飛躍を生んだのは、化石に残らない、微妙な因子だ。なんらかの要因で長寿命化したことで、知識が蓄積し、様々な文化がうまれ、言葉も進化した、とも考えられるし、なんらかの要因で言葉が洗練され、繊細な道具を数多く作れるようになり、食生活が改善し、人口が増加したとも考えられる。因果関係のパターンは無数にあり、おそらくそのどれもが、他の因子を強めるポジティブフィードバックのかたちをとることになっただろう。
飛躍のきっかけとなった要因が、遺伝的なものか、そうではないか、という点は興味深い問題だ。きっかけが遺伝子の突然変異だったという可能性はいぜんとしてある。なぜなら、脳の回線のわずかな変化によって飛躍的に言語能力が向上するということはありうるが、それは解剖学的な差となって化石にあらわれないからだ。
だがいずれにしても、ネアンデルタール人は言葉を持たなかったからホモ・サピエンスに敗れた、という考え方はフェアなものの見方ではない。その根拠をいくつか示そう。
言語を司る遺伝子FOXP2
まずはFOXP2について。
FOXP2とは言語能力とむすびついている遺伝子の名だ。イギリスに住むある家系の数十人が、3世代にも渡って、うまく言葉を話せない先天性の障害をもっていた。彼らの遺伝子を深く調べていくと、第7染色体に突然変異が見られることが判明する。この研究がブレイクスルーとなって、言語を司る遺伝子FOXP2の存在があきらかとなった。
ネアンデルタール人ゲノムもついに解読されてしまったので、おそらく人類学者はネアンデルタール人がFOXP2遺伝子を持っているか?という点にもっとも興味があっただろう。その結果は、「持ってた」である。
これをもって決着としてもよさそうなものだが、2015年に放送されたNHKスペシャル生命大躍進では、FOXP2遺伝子のわりと近くで、ネアンデルタール人ゲノムに変異が見つかったので、これが原因でホモ・サピエンスほどの言語能力がなかったのではないか、という見解だった。
その可能性もなくはないが、前述のように15万年ほども両者は似たような石器をつくり続けていたので、その説にそうならば、約4.5万年前ホモ・サピエンスにだけその部分に突然変異がおこり、一瞬でグループ内にひろがったということになる。
これが事実かどうかは、それ以前の人類のゲノムを解読できればあきらかになるだろう。わたしは4.5万年よりはるか以前からこの違いがあったと思う。つまり4.5万年前の飛躍の要因ではないと思っている。
ネアンデルタール人とホモ・サピエンスは交雑した
このテーマも長年の注目の的だったが、ネアンデルタール人ゲノムが解読されたことで、ネアンデルタール人とホモ・サピエンスのあいだに交雑があったかどうかもすでに判明している。その結果は、「現生人類ゲノムの約1-4%がネアンデルタール人由来」である。
つまり、ネアンデルタール人とわたしたちは交配したということになるが、その事実よりもっと重要なこととして、「わたしたちの直系の祖先は、ネアンデルタール人との間にできた子どもを育てた」という厳然たる事実がある。そうでないと、現生人類のゲノムにネアンデルタール人ゲノムが残されているということはありえない。ネアンデルタール人との間に産まれたこどもをすべて殺してしまったり、すべて部族から追い出したり、そういったことはなかったということを示している。そして当然のことだが、その間にうまれたこどもは、伴侶をえて、次世代にこどもを残すことができたのだ。われわれは彼らの子孫である。このことについては以前も記事に書いた。
わたしたちとネアンデルタール人は協力して子どもを育てた可能性すらある。なにしろ1-4%も遺伝子が残されているのだから。だとしたら、ネアンデルタール人がしゃべらなかったということがありえるだろうか?片親だけが無言だったら笑ってしまう。
もちろん、そういうこともありえないことではないだろうが、かなり不自然な考え方だ。
ネアンデルタール人はホモ・サピエンスの文化を真似た
最後に、わたしから見たら決定的と思われる例を紹介する。
後期旧石器時代になって、シャテルペロン文化とよばれる文明が発達する。この文明を発展させた者がだれなのか、長年議論の的だったらしいのだが、ネアンデルタール人の化石といっしょに遺跡が出土されたことで、確定的になった。シャテルペロン文化は、ネアンデルタール人によって繁栄させられ、かつての彼らにはつくれなかったはずの、高度な石器類をもつ。ホモ・サピエンスがヨーロッパに進出するようになってしばらくして興り、ネアンデルタール人が絶滅する直前まで続いた。このタイミングは、あきらかにホモ・サピエンスからの侵攻を受け、かれらは学習し、模倣し、対策を練ったことを示している。
言葉をうまく話せない集団が、この短期間でこのレベルの問題解決能力を発揮できるだろうか?

ネアンデルタール人がこのブログを読むときがくるかもしれない
ネアンデルタール人ゲノムがすべて解読された今、理論上はネアンデルタール人を現代によみがえらせることが可能だろう。そのとき、彼/彼女は言葉を話すようになるだろうか?わたしたちは再現可能な問題としてこのテーマで議論することができる。
「人間と同じように育てられれば、人間と同じようにしゃべれるようになる」
わたしなら絶対にこっち側に賭ける。わたしの予想では、彼/彼女は高校に入学すると、twitterアカウントも開設するだろう。記念すべきはじめのツイートはおそらくこんなかんじだ。ブラックなユーモアを添えて。
「4万年の時を経て復活しました!わたしの遺伝子をほろぼした人類に蘇らせてもらうなんて複雑な気分ね」
ネアンデルタール人が言葉を話したか、話さなかったか、各人が類推するのはもちろん自由だが、今や、ネアンデルタール人本人がその類推記事を読むということが理論上可能な時代にきている。そのとき、彼らにどういうメッセージが伝わるか、わたしは考えたい。そしてわたしのメッセージはこうだ。
「わたしはネアンデルタール人の才能を信じているし、彼らとともだちにもなりたい」
鳥を識る批評ー進化論の真髄が少しわかる批評
鳥類全般に共通する行動原理を知りたくて、「鳥を識る」で入門を果たした。鳥の生態について、ティンバーゲン的に言うと、至近要因と究極要因からの説明が充実していて、驚きの事実も散りばめられており、とてもおもしろかったと思う一方、つっこみどころが多すぎて批評を書く手をとめられなかった。
ひとつひとつ私の意見をぶつけておきたい。
コウモリは鳥に勝てるか?
恐竜が絶滅し、翼竜も絶滅した空にコウモリが進出して、夜の世界を中心に大きな勢力となりましたが、コウモリの呼吸法は一般的な哺乳類と同じで、鳥類よりも優れているわけではありません。もちろん、数千メートルの高高度も飛行できません。この先、コウモリががんばって進化して、さらなる大繁栄をすることがあったとしても、こうした資質で大きく差をつけられているために、空のシェアを鳥から奪う事はおそらくないでしょう。
まずは第2章、鳥類と哺乳類の呼吸法を比較しているところでコウモリは鳥に勝てないと言っているところだが、
free-tailed batとよばれるコウモリはなんと高度3000mで飛ぶという圧巻のパフォーマンスを披露する!*1
https://academic.oup.com/jmammal/article-abstract/54/4/807/844057?redirectedFrom=fulltext
ここで著者が言っている趣旨は「鳥類の方が哺乳類よりも呼吸効率がいい」ということで、それはおそらくそうなのだろうが、コウモリが「数千メートルの高高度も飛行できません」というのは残念ながらまちがっている。おそらくこのコウモリよりも飛ぶのが下手な飛翔性の鳥もいるだろう。
コウモリをあなどってはいけない。イルカ、シャチ、クジラらの呼吸効率が魚類よりも圧倒的に悪いのは明らかだが、彼らが海で繁栄しているのを見ると、進化における競争は総合力がものをいうことがわかる。
なぜ恐竜は絶滅し、哺乳類と鳥類は生き延びたのか?
だとしたら、生き延びた種と絶滅した種を隔てたのは、何だったのでしょうか?その理由として最初に指摘されるのが当時の鳥類と哺乳類の平均的な体のサイズと繁殖スピードです。
次も同じく第2章、大絶滅時代に恐竜は滅びたが哺乳類と鳥類はかろうじて生き残った、その差を分けたのはなにかというミステリーに言及する箇所。
体のサイズが小さいことは激変する環境への適応に有利だ。その理屈はr/K淘汰として説明できる。過酷な自然環境を生き抜くのに重要な要素は、個体数が多いことである。数が多いとそれだけで絶滅をまぬがれる確率が高くなるし、環境に適応する者が出現する確率も高くなるだろう。そのため多産で、早熟であることが非常に有利となる。そして、限られた資源のもとで数を増やすためには、体の大きさを小さくせざるをえないというわけだ。
隕石や火山による劇的な気候変動を生き残るためにそれが重要だったという考えは私と同じだが、なぜ「平均的なサイズ」が重要なのだろうか?鳥は空をとぶために小型化したので平均的に鳥類は小さかったというのはおそらく正しいが、それは鳥類は小型の恐竜から分岐したということの裏返しでもある。われわれは通常恐竜というと巨大なものをイメージするが、小型の恐竜もたくさんいたはずだ。ここでの議論で「平均的なサイズ」を持ち出すのは、巨大な恐竜が小型恐竜のあしをひっぱって道連れに絶滅させた、というおかしな主張にきこえる。
この説明では、鳥類、哺乳類と恐竜の命運を分けたものがなにかという根本的な問いに向き合えていない。
ヒトが器用な腕や指を捨てるとき
これは1つの仮定ー想像ですが鳥の祖先の恐竜が、何らかの要因から、ものをうまく握ることができる手や指、抱きしめることのできる柔軟な腕を先に身に付けていたとしたら、人間が手を手放したいとは思わないように、彼らはその便利な手を翼にしようとは思わなかったのではないでしょうか。
第3章、飛翔の進化にせまる章であげられている一文。
ただの想像だというのはわかるのだが、 この一文を読むと、著者は自然淘汰の威力をあまりわかっていないのではないかと思えてしまう。鳥の翼はわれわれから見ると、ものすごく優れた発明に思えるが、ダチョウ、キウイ、ペンギンなどいとも簡単に”飛ぶため”の翼を捨ててしまった鳥はたくさんいる。鳥が簡単に飛行能力を捨てられるのだから、手や指についてもそうできるだろう。一応私たちの腕も、数億年前は泳ぐためのヒレだったのだから。
鳥類に長寿のアロメトリーは成り立つか?
動物の心臓が一生の間にうつ総数は一定で、心拍数の少ない動物ほど長生きと、「ゾウの時間 ネズミの時間」などでは示されていましたが、それは基本的に哺乳類に限ってのことで、鳥類には当てはまりません。
こういった断定口調にあやしさを感じたので念のため調べてみたが、鳥類の代謝率と長寿のアロメトリーを調べ直した論文がすぐ見つかった。
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2527636/
この論文では、当初鳥類ではアロメトリーが成り立たないと思われていたが、調査対象母数が少なかったので増やしてみたら哺乳類同様の相関が見つかったとある。
動物たちはなぜ群れるのか?
生き延びると言うことに関して、動物は極めて利己的です。特に体の小さな鳥にとって利己心は不可欠と言って良いもので、猛禽類や肉食哺乳類に襲われた場合、自分以外の群れの誰かが犠牲になってくれれば自分が助かると言う意識を持つのも、鳥にとってごく自然なことです。サイズが近く、食性が近い異なる種が混群を作るのも、大勢でいれば自分が殺される確率が減らせると言う意識がうちにあればこそです。
群れが敵に襲われたとき、(つがい相手以外の)誰かが犠牲になることで自分が助かれば良いと考えるように、鳥は自己中心の思考をします。エゴイスティックではありますが、それが生物の本質でもあります。
第5章、このあたりから個人的にかなり反論したいことが多く、読み進めるほど不機嫌になってしまった。
まず、動物は極めて利己的という主張。
(あたかも人間は利己的ではないという含意も感じるが)私は著者がドーキンスの「利己的な遺伝子」を読んでいないか誤読していると疑っているが、とりあえずその話はあとでするとして、ここでは「大勢でいれば自分が殺される確率が減らせる」という論理にかみつきたい。
これは本当にそうなのか?すんなり受け入れられそうにも思えるが、疑ってかかるべき類のものだ。
仮にある鳥Aをメインに捕食する肉食動物Bがいるとしよう。肉食動物Bが一定の数存在し、Bが食べる量は一定だとすると、犠牲になる鳥Aの数も一定ということになる。大勢でいるだけで殺される確率が減るということはない。大勢でいれば、一度の狩りで犠牲になる確率は低いかもしれないが、その半面大群でいるがゆえに遠くからでも敵の目をひきつけやすいため、狩りの回数、狙われる回数が増え、結果的に殺される確率はかわらないと考えられる。むしろ、Aの大群がBにとって格好の標的になったら、おなかいっぱいになるまで狩られることになり、全体としての死亡率は上がるかもしれない。
動物が大群でいるのには、大群でいるだけの理由がある。その理由は種によってさまざまだろうが、天敵とたたかうという観点で言うと、興味深い例を見たことがある。
ある動物ドキュメンタリー番組の一節だったが、おなかをすかせたアシカが魚の大群を追い込み、群れにつっこんでいくのだが、魚の群れ全体が調和をなして急激に方向転換する様子に目がくらみ、結局一匹もつかまえられないまま狩りをあきらめたのだった!あのアシカが!魚を目前にして!
グループが調和を保って行動すると、ハンターは狙いを定めにくいのだという。
つまり、大群は大群でぼーっとしてるのではなく、互いに協力することによって、一個体は利益を得られるのだ。だから群れをつくる動物がいるのだ。彼らは群れを維持するために、いろんな努力をする。その中には互恵的利他主義とよばれる目を見張るやさしさを見せる種もいる。
さて、「大勢でいれば自分が殺される確率が減らせるか」という問いに私なら「YES」とこたえる。これそのものは実は著者の主張と同じなのだが、なぜそう思うのか、の背景にあるものが全く逆なのだ。わたしはあくまでも、「群れる動物は互いになんらかの協力関係にあるからこそ、生存確率を高めることができている」と思っている。著者は、「なぜ群れるのか」の問いに「自分以外の群れの誰かが犠牲になってくれれば自分が助かるから」というこたえをあげているが、これが理由になるのだったら、「別に群れなくても、目立たないようにしていて誰かが犠牲になれば自分は助かる」というこたえもまっとうな理由になる。
極端なことをいうと、もしわたしが、「自分以外の誰かが犠牲になればOK」という考えの持ち主なら、スキを見てとなりにいる人を羽交い締めにして敵に差し出す。しかし考えてみてほしいのだが、そういうことが横行するグループで果たしてそれでも群れでいなければいけない必然性があるのだろうか?虎視眈々と相手をだしぬくことしか頭にない利己的な集団は、危険すぎて集団を形成できない(天敵といっしょに群れを作ってるようなもの!)。単独行動してたほうがマシだ。そう考えると、著者の「群れ」に対する見解は、「なぜ群れるのか」という本質にまったくせまれていないと言える。
「擬傷」を進化論で説明する
人間的と感動する一方で、我が身を犠牲にしかねないこうした行動をどう受け止めたらいいのか理解に悩むかもしれません。その際は、こうした例を、「次善の策」と考えるとわかりやすいように思います。自分の遺伝子を残すのがいちばんであるものの、どうしてもそれができないときは近い遺伝子を残し、それすらかなわない時は同種の誰かが生き延びるようにする。
同じく第5章、ここの文章は鳥類に見られる「擬傷」とよばれるおもしろい行動の説明のあとに出てきたものだ。擬傷(ぎしょう)というのは、子育て中の鳥の巣の近くに肉食動物が近寄ってきたときに、親鳥があたかも怪我をしたようなフリをして、肉食動物の興味をひきつけ、巣から十分離れたところにまでおびき寄せてから、さっと逃げてしまうという自然界の一幕の話である。実際にこの習性をもつ鳥がいるのだから驚きだ。。
自分が危険をおかして子どもを守るというヒーローのような行動は、進化生物学者の間でもたしかに問題となっていたようだ。しかし、なぜ、擬傷というすばらしい利他行動の説明のために「次善の策」というアイデアを持ち出すのだろう。もし本当に動物にとって自分の遺伝子を残すのがいちばんなのだったら、自分を守ることが最優先事項となるはずだ。捕食者が近づいてきたときに子どもだけおきざりにしてさっさと逃げてしまったほうがいい。「次善の策」の理屈で考えればそうなる。
リチャード・ドーキンス「利己的な遺伝子」を読めば、自然淘汰のメカニズムがそうシンプルではないことがよくわかる。多くの人は、このベストセラーのタイトルだけ見て、「動物は自分の遺伝子のコピーを残すように利己的に行動する」のだと思うかもしれない。それがそうでもないことを懇切丁寧にドーキンスは教えてくれる。もし、自分の遺伝子のコピーを残すことが至上命題なのだったら、有性生殖という仕組み自体がまったく理にかなっていない!!有性生殖(つまりオスとメスが交配してこどもを作るしくみ)で子どもに伝わる遺伝子はたったの50%しかない。それに対して無性生殖では100%。まさに自分のクローンを作り出す生物は自然界にはたくさんいる。ドーキンスはそのことをはっきりと提示した上で、「遺伝子とはなにか?」という深淵な問題に立ち向かっていくわけだ。その後の論理展開は、私が知る中でこの世でもっともおもしろい知の探求のストーリーとなるのだが。。
私はぜひ多くの人に利己的な遺伝子を我慢強く読み解いてほしいと思っているが、その話はここまでにしよう。ここで声高に言っておかなければいけないことは、「遺伝子が利己的であるがゆえに、個体(動物)が利他的になる」という事実である。
「次善の策」という説明はドーキンスの劣化版にすらならないどころか、彼のメッセージをねじ曲げてさえいる。
言葉をしゃべるのは人間だけという固定観念は過去のもの
一方、哺乳類では、発声学習するのは、人間と、イルカクジラの仲間、鯨類のみです
ここから第6章だが、個々にはおもしろい事例も多いのだが、章全体の方向性がかなり迷走してるように感じる。
鳥類の特筆すべき能力の一つ、発声学習について掘り下げたところで、哺乳類では人間と鯨類しか発声学習しないと主張しているのだが、事例を知らないだけのように思える。
近年、動物がとても豊かな感情、知性を持っていて、豊かにコミュニケーションとっているということが認知されつつある。フランス・ドゥ・ヴァールに代表される学者らの功績によって。そうした背景にあって、人間しか言葉をしゃべらないという動物学者はもういないだろう。いくつもの動物の「言葉」が明らかになりつつある。
私が知るところでは、ベルベットモンキーの警戒音の研究がもっとも有名な、「動物も言葉をもっていること」を証明した研究だ。ベルベットモンキーは、「ヒョウ」、「ヘビ」、「ワシ」といった、タイプ別捕食動物それぞれに対応する警戒音を発していた。誰かが「ヒョウ音」をならすと木に登って避難し、「ワシ音」をならすと空を見上げる、といった具合に。これらの「音」と「自然界の対象物」の結びつきを、遺伝的に生まれもっているというのは考えにくい。実際、こどものベルベットモンキーは大人が発した警戒音に対してしばしば間違った行動をとることがあったという。ということは、ベルベットモンキーは発声を学習している。
人間と鯨類しか持たない発声学習とは、ベルベットモンキーのそれと、本質的に何が異なるのか問いたい。もちろん程度の差があることはわかるが。
性淘汰で進化した鳥とヒト?
哺乳類には理解しがたい鳥類の選択
人間だけが理解できた鳥類の選択
一般的な哺乳類では、それが好きか嫌いかなどを考えたりしないような対象や状態に、人間や鳥は引っかかり、「好きか嫌いか」「これとこれならどちらがいいか」と判断する心を持っていました。
同じく6章のタイトルや文中からの引用で、あたかも人間と鳥類だけが審美眼を持っていて、それ以外の哺乳類は持っていないと言いたいそうな謎の自信である。人間以外の哺乳類をそこまで軽視するのはなぜなのか。
おそらく著者は、次で説明するように、性淘汰という原理が、鳥類と人類にだけはたらいていると思っているのかもしれない。
しかし、鳥が鮮やかである理由の全てを性淘汰で説明することはできません。なぜなら、インコやハチドリなど、熱帯や亜熱帯に生息する鳥を中心に、オス・メスともに派手な羽毛をしているものが数多くいるからです。
前の引用にも関連して、ここでテーマとなるのは、鳥類の「性淘汰」についてである。性淘汰について簡単に説明すると、
ある動物グループのメスの多くが何らかの理由で、尾が長いオスを好むようになったとする。すると、「尾が長いオス」が子孫を残しやすくなる。彼らの子孫は遺伝的に「尾が長い」であったり、「尾が長いことを好む」傾向が出てきて、一気に進化のポジティブ・フィードバックがはたらき、メスの好みによって形質の進化がおこるという理論である。
ダーウィンが、クジャクの羽根の進化をなんとか説明するために、やむなしで生み出したのが性淘汰理論のはじまりだったが、ダーウィンの死後、長らく進化生物学の表舞台からは消えていた。ところが近年、性淘汰の理論的可能性が検討されはじめたり、それがはたらいたとしか思えないような事実が見つかったこともあって、私も内心、性淘汰は進化論のかなり大きな部分を占めているメカニズムだと思うようになった。特に鳥類の進化においては、性淘汰ぬきには語れそうにない。本書の著者もそう思ってるだろう。
だが、著者は「性的二型(つまり、オスとメスの見た目が著しく異なること)をもつ種だけが、性淘汰の影響下にある」と思っている点が私の考えと異なる。前述の性淘汰の原則に沿って考えれば、メスのオスへの好みが「自分自身の外見と著しく異なっていること」である必要はないように思える。逆に、「自分の外見となるべく同じような異性を好きになる」性淘汰もあるだろう。ゴリラ / チンパンジー / ヒトの順に、性的二型が緩和されていく流れも、性淘汰の範疇にある気がしている。これはとりわけ、オスとメスが協力して子育てをしなければいけない、といった事情と関係しているかもしれない。
鳥類と人類にだけピンポイントに性淘汰がはたらいている、そしてそれは彼らだけが審美眼を持っていたからだ、という主張は、演繹的すぎる。マンドリルの顔やおしりがあれほどまでに鮮やかなのはどう説明するつもりなのか?
脳のサイズやしわで知性を判断できるか?
鳥が、本来よりもずっと低く見られてきたのは、人間の矜持から来る、ある種のおごりと、人間基準の物差しだけで鳥を評価してきたことが大きく影響しています。自身を万物の霊長と呼び…
鳥の知性にせまる第7章。
この引用では、その前段で、鳥の知性がかつて非常に軽視されていたという嘆きにつづいている。鳥を解剖したところ、しわのない脳が出てきたことから、哺乳類脳ばかりを見てきた従来の学者は「取るに足らない知性の持ち主」と判断したらしい。それについて、これは人間のおごりだとして、強くいましめるメッセージが続くのだが、この著者は過去の人間の失敗を自分のこととして捉えて、次に自分がどういう立場をとるべきか熟考していないように思う。
典型的な例として、「脳のしわの数で知性を判断するな!」という厳しい叱咤の直後に、あろうことか動物ごとの脳のサイズの比べっこをしていて、グラフまでのせている。あたかも、「鳥類は脳のサイズが大きいから哺乳類よりも頭がいい」と言わんばかりの。「体重に対する脳重量の比率で知性がわかる」という主張は、「脳のしわの数を見て知性がわかる」と言ってるのと大差ない(たしかな根拠がない限りは)。そんなものの妥当性は、新たな発見で棄却される未来がわたしには見える。
動物は人生を楽しむか?
鳥のさえずりは伴侶を得るためか、縄張りの主張のためのもの。とにかく声を出し続けることに必死で、楽しむ余裕などないからです。多くの鳥は、人間のように歌うことを楽しんだり、自分の歌声に酔う事は基本的にしないと考えてください。
鳥の心について言及する第8章。
ここでもとくになんの根拠も示さず、「鳥は楽しんだりしない」と断言的に書いているのだが、これによって読者になにを伝えたいのか理解に苦しむ。(実際、鳥たちが楽しんでるようにしか思えない事例をいくつも著者自身が本書で提示している。)
ライオン、トラ、キツネなどの赤ちゃんが、兄弟たちと四六時中狩りごっこをしてるのをドキュメンタリー番組でよく見るが、私には楽しそうやなーという感想以外のものが出てこない。狩りごっこが楽しくてしかたないんだろう。
ゴクラクチョウ科の鳥には誰も見てないのにダンスを踊るものがいる。求愛の練習をしてるにしても、ひとりで楽しくなっちゃってるんじゃないだろうか。下手すると求愛相手のことを想像してウキウキしてさえいるかも。
これらの例は憶測にすぎないにしても、昨今の動物心理研究の動向を見れば、あきらかに動物が心をもっているとしか思えないような事例が次々と見つかる流れにある。動物の心や知性をテーマにしたまとめ本として超絶おすすめできるのは、「数をかぞえるクマ、サーフィンするヤギ」だ。写真もたくさんのっていて最高にいやされる。
わたしたちが、「おいしい」と思うから「食べる」ように、「楽しい」と思うから「遊ぶ」し、「練習する」。これと同じメカニズムが人間にあって、動物にはないという考えはあまりにもナンセンスで、進化論を否定しないかぎりそんな結論は出せようがない。
進化論の説明をする際に非常に重要な要素として、「動機の独立性」があるとドゥ・ヴァールも言っている。動機の独立性とは、たとえばカエルは求愛のためにケロケロなくが、彼らはその行動の目的を「求愛のため」だと意識している必要はないということだ。そうではなく、ただ単に「楽しいから鳴く」のであっても、結果的にそれがメスを惹き付けるのであれば、自然淘汰はそういう形質を維持するように作用する。
藤井聡太は今将棋界をにぎわす人気者となったが、彼はモテたいから将棋を始めたのか?結果的に大人気ものになったとはいえ、当初の動機はそうではないだろう。
この議論は、今後ますますどうぶつたちの人っぽさがわかるようになるうえでも、重要な位置をしめることになると思う。以前、ブタの子どもを育てるトラが話題となった。進化論的に考えればきわめておかしな行動だ。獲物となるはずのブタを獲物とせず、自らの莫大なエネルギーをかれらのために費やすのだから。こういった行動も、動機の独立性を考えればおかしなことではない。私たちを含め動物は、自分が産んだこどもだけをかわいがるように厳密にプログラムされているわけではない。そしてそうあることこそが、多様性の源となる。
文明へと向かう動物
鳥は文明をのぞまない
鳥を含む人間以外の動物は、ほどほどで満足しました。でも、人間は満足せず、さらに楽や便利の先を求めた。
最後に、道具をつかう鳥類の行動に言及した直後の謎の断言。
動物が道具を使っていることがわかっている時点で、文明をのぞんでいる、文明へと向かう途上にいるという発想はできないのだろうか。キツツキフィンチ、カラス、シャカイハタオリ、ツカツクリ、...などといった鳥類はあきらかに、延長された表現型として、自然を克服しようとする一歩目を踏み出している。それが分かっていないことこそ、人間中心の思考からはなたれていないことの証左のように私には思える。
さいごに
いろいろと書いたあとでこういうのもなんだが、それでも本書はおすすめできる。客観的に書かれている箇所はかなりおもしろいので。

- 作者: リチャード・ドーキンス,日高敏隆,岸由二,羽田節子,垂水雄二
- 出版社/メーカー: 紀伊國屋書店
- 発売日: 2006/05/01
- メディア: 単行本
- 購入: 27人 クリック: 430回
- この商品を含むブログ (197件) を見る

数をかぞえるクマ サーフィンするヤギ―動物の知性と感情をめぐる驚くべき物語
- 作者: べリンダ・レシオ,中尾ゆかり
- 出版社/メーカー: NHK出版
- 発売日: 2017/12/23
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログ (1件) を見る
*1:Williams, T. C.; Ireland, L. C.; Williams, J. M. (1973). "High Altitude Flights of the Free-Tailed Bat, Tadarida brasiliensis, Observed with Radar". Journal of Mammalogy. 54 (4): 807.
罪は憎むもの、人は憎まぬもの
何か事件があると、したり顔で「罪を憎んで人を憎まず」などとほざく人間がいたりするが、そうではなく「人を憎んで罪を憎まず」だろう。犯人は死刑及び重罪に課すべきだが、罪である行為は、その精神的あるいは社会的な背景を調べ、問う必要があるからだ。
— 千坂恭二 (@Chisaka_Kyoji) 2016年7月27日
善悪に対するわたしの考えは自分で言うのもあれだけどとってもピュアだ。
「"罪"を憎んで人を憎まず」
「みんな違ってみんないい」
の2つでほぼ言い表せる。
このコメントを見ておもしろいなと思うのは、結論は千坂さんと全く同じなのに、その表現の解釈が全く逆になることだ。
わたしの感覚だと、「罪」を徹底的に憎まなければ、「その精神的あるいは社会的な背景を調べ、問う」ことはできない。憎むべき対象が「その人」なのだったら、とりあえずめんどうだからこの犯人を罰したらよくない?で終わる。「罪」を徹底的に憎むからこそ、その人を罰するに留まらない恒久的な対策への衝動が生まれる。
とは言え、わたしはこのコメントを見るまで気付かなかったが、たしかに「罪を憎んで人を憎まず」という言葉はあいまいな言葉に聞こえる。特に「憎む」と「人」が何を指すのか人によって解釈がかわりそうだ。
たとえば、「憎むべきもの」を「あってはならないこと」とおきかえる。
そう考えれば、「あってはならない」のは、罪である「行為」の方である。「人」はあっていい。「行為」の対照となるのは、行為を生み出す人間の属性、すなわち「形質、性質、特徴」のようなものである。
つまり、「”行為”を憎んで”特徴”を憎まず」があるべきものだと思う。
「形質、性質、特徴」は、極論すればヒトのDNAである。
遺伝子配列それ自体に、善も悪もあるだろうか?憎むべきものとそうでないものがあるのか?存在していいものとだめなものがあるのか?生まれか育ちかの議論はここでは関係ない。いずれにしても、ある特徴をもつに至る過程は運命に依存する。
「形質、性質、特徴」は、それ自体に善悪があるはずがない。「行為」となって表に現れてはじめて、(少なくとも主観的には)善悪の概念を帯びてくる。当然ながら、同じ「形質、性質、特徴」を持った人が善悪的に正反対の「行為」をおこなうこともある。
そうである以上、憎まれるべきものはあくまで「行為」の方である。*1
「人を憎め」というのは、場合によっては「生まれたばかりの赤ん坊を憎め」ということでもある。そんなことできます?
わたしは今のところ死刑制度廃止論者ではない。
人を憎まずに死刑賛成というのは矛盾していると思われるかもしれないが、わたしはたぶん刑罰を「罰」として捉えていない。
「人を殺してみたかった」という異常な動機で殺人を犯してしまうサイコパスに対してのわたしのスタンスは、
「
あなたにそう思わせようとする脳も、あなたにそう思わせようとする脳を作ったDNAも人生も、それ自体は決してあってはならないものではなかった。
けれども、それを実行に移す主体とわたしたちが同じ世界で生きていくことはできません。
わたしたちは、わたしたちを守るために、あなたを殺します。
ごめんなさい。さようなら。
」
ということになる。
人を憎む憎まずに関係なく、結局死刑に処せられるのであればどっちも同じじゃないかと思われるかもしれない。
けれども、人を憎むか憎まないか考えることは将来、「殺人鬼とあなたのDNAは○%の割合で似ています」といったDNA調査をできるようになり(既にそういう闇サービスがあるかもしれない)、その存在を許すか許さないか、という議論が噴出したときに意味を持つ。そういうことがわかるようになると必ずうろたえる人々が出て来て、今までになかった差別軸が現れる。DNA差別である。
その勢力に負けると、選民思想社会が完成する。
わたしたちは強い心をもって「みんな違ってみんないい」と言えるようにならなければいけない。
*1:ただし、もしもある凶悪な行為を100%実行する形質が存在することが明らかになった場合、その存在を認めることはできないだろう。何をもって100%と断定できるかは微妙だが。
私が金正恩だったら
朝生見てたら、「トランプ大統領の今回の北朝鮮へのやり方に」「賛成」が61%という結果が出ていた。

現在北朝鮮は核実験を成功させ、核爆弾を推定20個ほど保有しているらしいが、これを長距離弾道ミサイルに搭載して標的を攻撃するという能力までは持っていないらしい。中長距離弾道ミサイルは一度大気圏を出てから落下してくるらしいが、そのとき空気抵抗によりものすごい熱を発するため、弾頭の攻撃能力が失われるという。*1これを避けるためには高度な技術が必要で、その開発に北朝鮮はまだ追いついていない。そのレベルに達するのに早くとも4,5年かかると見られているという。
という背景があるので、「金体制を潰すなら今しかない」という先制攻撃案をとなえる人もいる。冒頭の投票結果、賛成61%という数字が出るのもそういった背景があると思われる。
しかし、本当に北朝鮮を潰すようなことができるのだろうか?
米軍が先制攻撃し、一気に平壌制圧までの戦争を始めたとしよう。
わたしが金正恩となって全力で金体制崩壊の阻止をこころみたい。
***
どんな奇襲であっても北朝鮮にとっては想定内である。いくつかの攻撃拠点は破壊されるが、速やかに反撃する体制は整っている。ソウルに向けられた大量のミサイルが発射される。同時に朝鮮戦争が再開。ミサイルの応酬が繰り広げられ、陸空で戦火が飛び交う。北朝鮮も大きな被害を受けるが、ソウルは首都機能停止状態に陥る。
一方で、北朝鮮は米空軍から猛攻撃を受ける。
北朝鮮はおそらく空中戦ではアメリカに全く歯が立たない。ゆえになるべくアメリカに的を絞らせず、ミサイル攻撃と同時に分散させて空軍部隊を出動させる。狙いは東京への空襲である。おそらく高確率で全機が東京に辿り着く前に米軍または自衛隊が撃墜するだろう。しかし、ミサイルをすべて迎撃できるかといえば、かなり怪しい。
日本では携帯が警報を鳴らす。空襲警報とミサイル警報である。
はじめの20発のミサイルはすべて迎撃に成功し、そのニュースが日本で大々的に報道され、twitterのタイムラインは異様なテンションとなりナショナリズムが盛り上がる。
しかし、次の20発のミサイルのうち1発が迎撃をのがれ本州内に着弾する。化学兵器や核爆弾搭載ではなかったが、死亡者が出て日本に戦慄が走る。日本のtwitterでは「もしこれが核爆弾だったら...」といった動揺がひろがる。
ところが、北朝鮮にとっては40発に1発しか着弾しないミサイル攻撃ではらちがあかない。そうこうしている間にも北朝鮮は米空軍の猛攻撃を受け、攻撃拠点がどんどん破壊されてゆく。「北朝鮮の降伏も時間の問題だ」と専門家が言い始める。
実は、これら北朝鮮の戦闘機とミサイルによる東京攻撃はどちらもおとりである。本当の狙いは工作員による核攻撃である。実は、ミサイル攻撃・空軍出撃に前後して、漁船に扮した工作員部隊を100船出撃させていたのである。そのうち10船は日本海上保安庁に確保または保護されるが、戦闘機およびミサイル攻撃対応に気をとられた日本は90船の工作員部隊の侵入を許す。そのうちの3船が核爆弾を積んでいる。
核を積んだ1つの漁船は、日本海側のなるべくでかい都市、たとえば福岡の港につける。そこで工作員は核のスイッチを押す。(この工作員は死亡するが、北朝鮮内で英雄として扱われ、彼らの家族は生活を保障され、名誉を受ける手はずになっている。)日本はもちろん、世界中に動揺が広がり、連絡網はダウンする。福岡市民は、私の友人知人も含め10%が即死する。
この大厄災に焦ったアメリカはすぐさま金政権との話し合い画策する。事態を重く見た中国が両者を仲介し、北京に会談の席を設ける。ここで金政権はさらに世界を驚かせる。「あと2つ、日本に核爆弾を持った工作員を潜入させている」と。
歴史的大事件となるこの北京条約で、アメリカは北朝鮮の金体制援助を約束するのである。
***
さて、このシミュレーションの北朝鮮はなにがしたかったのだろうか?
それは、「一撃講和」である。旧日本軍が第二次世界大戦で呪われたように固執した終戦にいたるまでの戦略である。自軍にいくら被害をこうむってもよいから、敵に強烈な一撃をくらわす作戦を成功させるのである。相手がひるんだところで講和に持ってゆき、なるべくいい条件で戦争を終結させるのだ。
旧日本軍は一撃講和をやろうとして失敗し続け、だらだらと戦争を長引かせ、多くの戦死者を出すことになった。だが、現在の北朝鮮は旧日本軍と条件が違う。敵対する韓国や日本の本土が目の前にあり、しかも核兵器を保有している。したがって一撃講和という戦略がワークする可能性がある。逆にいえば、アメリカが先制攻撃にふみきった場合、北朝鮮は金体制を守るためにこの作戦を成功させるしか道がないため、そこに全力を投入してくる。
工作員による玉砕覚悟の核攻撃は可能だと森本氏も朝生の中で言っている。なのでふつうに考えれば先制攻撃なんてことはできない。
さっきの例では福岡が標的となったが、韓国が核や化学兵器の標的になることははるかにかんたんに推測できる。つまり、「武力制裁に賛成する」というのは、「私は少なくとも韓国は見捨てます」というメッセージに非常に近い。韓国を見捨てておいてアメリカには守ってもらえると信じているのもおかしいし、こういう世論調査結果を出すことが韓国の日本への絶望感をたかめている可能性にもうすこし配慮したほうがいいと思う。
突然変異で進化はできない。進化論最大の謎に突破口を開いた研究
「進化論」という理論をはじめて知ったのはたしか大学のときだった。「自然淘汰」と「突然変異」という超シンプルな原理で多様な生物の誕生を説明できてしまうことに衝撃を受けた記憶がある。
しかし、ダーウィンが唱えた進化論は「自然淘汰」が中心で、「突然変異」という概念は出て来なかった。ダーウィンが生きていた時代には、遺伝子という概念さえも未発見だったため*1、突然変異といった発想が困難だったと思われる。したがって、ダーウィンは「どのようにして生物は新たな形質を獲得するのか」という大問題には触れなかった。自然淘汰だけでは生存に有利な個体を”選別”することはできても、生存に有利な形質を”つくり出す”ことはできないのである。
時代は流れ、今や生命を司るセントラルドグマ、DNAの存在が明らかとなった。これによって「突然変異」の仕組みが明らかとなった。つまり、「ランダムにDNA塩基配列に変更が起こり(突然変異)、そのうち『偶然にも』生存に有利だった形質が保存される(自然淘汰)」という説明がなされるようになったのである。これがダーウィン進化論の強力な援護となった。
と思われた。
が、突然変異が進化を促すという説明は全くもって不十分であるばかりか、間違っている可能性すらある。後述するが、理論的に大きな穴がある。
「進化論」でググると分かるが、この点を巡って大混乱が起きており、2017年現在は検索結果1ページ目の約半分が反進化論を支持するというとんでもない状況になってしまっている。(個人的には、突然変異による進化が説明できないからと言って、進化自体を否定するのは乱暴すぎる気はする)
この科学の空白地帯にビジネスチャンス?を見出した人々が、宇宙人や神による生物創造説を提唱しているが、私にとって身近な例だとエホバの証人がある。彼らは熱心な布教活動をしていて丁寧な冊子を配っているので私にも分かるのだが、明確に突然変異による進化を否定している。彼らは進化を「大進化」と「小進化」に分けて考えていて、イヌからチワワ、ゴールデンレトリバーなど様々な品種が生まれる「小進化」は認めている一方、サルがヒトに進化したり、爬虫類が哺乳類に進化するような「大進化」は認めていない。意地悪い言い方だが、宗教上、現代の科学をどう解釈するかというこの戦略は巧みである。なぜなら大進化を説明する化石はほぼ見つかっていないし、突然変異の蓄積で生物に大進化を起こすことなど不可能に近いことが数学的に示されるからだ。
「 突然変異による進化は不可能」という問題提起から始まるのが「進化の謎を数学で解く」である。難しそうな内容だから軽く読み流すだけしてみようと思って購入すると異常なおもしろさで驚愕した。タイトルが心理的障壁を上げている気がする。本書に数式は一切出てこない。
なぜ突然変異による進化が不可能なのか。この本の冒頭で示される「ハヤブサの眼」の例がとてもわかりやすくエキサイティングな内容なのでこれを引用しつつ解説したい。
ハヤブサは獲物を狩るために突出した解像度の眼を持つ。1キロメートル以上の距離からハトを捉えられるという。この芸当を可能にするのは、クリスタリンという透明なタンパク質によるという。これがレンズの役割を果たし光を屈折させ、像を結ぶ。
多く見積もっても、生命が地球に誕生してから30億年が経ってようやくクリスタリン搭載の脊椎動物が現れた。つまり、地球上の全生命が突然変異/自然淘汰を繰り返して30億年後にクリスタリンを生成できる確率はいくらか?というクイズを考えることで、「突然変異による進化の可能性」を検証できる。
そのシミュレーション結果は散々である。
クリスタリンは数百のアミノ酸が鎖状につらなるタンパク質である。アミノ酸は20種類のパターンがあるので、DNAからランダムにクリスタリンを発現させようとすると、20の数百乗の確率になる。これは超々々天文学的な数字だ。宇宙に存在する水素原子の数よりもさらに気が遠くなるほど大きい数となるらしい。こんなオーダーでは、どんな理屈をこねくりまわしても、わずか30億年で”ランダムに”高精細レンズという奇跡的な形質を獲得するなど到底不可能である。ちなみに、クリスタリンがタンパク質のなかでとくべつアミノ酸鎖数が多いというわけでもない。生物を構成する器官はクリスタリンにとどまらず奇跡のタンパク質めじろ押しである。
この事実を知ると、エホバの証人説はもちろん、宇宙人想像説も全くバカにできなくなる。彼らが神秘主義にこたえを見出そうとするのはもっともなことだったと思い知らされた。
けれども、本書はもちろん神秘主義的な本ではなく、進化論を支持する。驚くべき研究で。生命の多様な進化は必然だったのではと今になっては思う。そしてここで紹介される研究を目の当たりにすると、いよいよ神秘主義者たちのアイデンティティが危うい。この著者は進化論最大の謎に風穴を開けた。
私は本書を読んで、中間の長さの首を持つキリンの化石が見つかっていない理由も分かったような気がする。その理由はたぶん、首が伸びるという進化が驚くほど短期間で起こったためだ(ウイルス進化説ではなく)。
生物のDNAは絶えず揺らぎを続け、進化が止まっているように見える生物でも、DNAの潜在的な多様性は時間と共に高まっていく。そして機が熟すと進化は短期間で一気に進む。
本書読まれた方はこの意図が分かるかもしれない。興味ある人はぜひ読んでほしい。

- 作者: リチャード・ドーキンス,日高敏隆,中島康裕,遠藤彰,遠藤知二,疋田努
- 出版社/メーカー: 早川書房
- 発売日: 2004/03/24
- メディア: 単行本
- 購入: 10人 クリック: 112回
- この商品を含むブログ (50件) を見る
*1:正確にはメンデルが遺伝子の存在をほのめかす重要な発見をしていたが埋もれていたらしい






